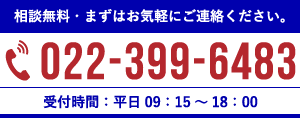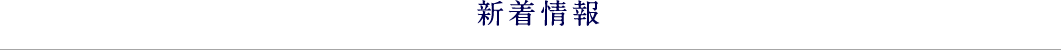消滅時効
1 契約に基づく債権
消滅時効とは、ある債権について、権利者が権利を行使しないまま一定期間が経過した場合に、その権利を消滅させる制度をいいます。
改正前の民法では、当事者間の取引(契約)に基づく債権について、「権利を行使することができるときから10年」で時効消滅するとの原則を置いていましたが、別途、職業別に様々な時効期間が存在しました(飲食料・宿泊料:1年、小売商人・卸売商人等の売掛代金:2年、医師の診療報酬:3年など)。
そのため、各取引について、どの時効期間が適用されるのか分かりにくいとの批判があり、改正民法では、以下のとおり時効期間を統一しています。
(原則)
権利を行使することができることを知った時から5年、または
権利を行使することができる時から10年
Q 「権利を行使することができることを知った時」と「権利を行使することができる時」の違いは何でしょうか。
A 「権利を行使することができることを知った時」とは、権利者の主観(その事実を知ったかどうか)を基準にするため、「主観的起算点」と呼ばれます。
これに対し、「権利を行使することができる時」 とは、権利者の主観ではなく法律上の状態(法律上の権利行使が可能となったこと)を基準にするため、「客観的起算点」と呼ばれます。
通常、主観的起算点と客観的起算点は一致することが多いですが、以下のような場合には、この2つがずれるケースも考えられます。
(例)労災により労働者が死亡したが、後日、その原因として会社の安全配慮義務違反が存在したことが明らかになったとき
客観的起算点:事故日
主観的起算点:安全配慮義務違反に当たる事実を知ったとき
(例)宅建業者が中古住宅の売買を仲介したが、重要な事項についての説明を忘れており、後日、買主が買い替えのために他の仲介業者に相談して説明義務違反が判明したとき
客観的起算点:当初売買時
主観的起算点:説明義務違反に当たる事実を知ったとき
(例)事業拡大のため、ある会社のオーナーから全株式を買い受け、「会社には簿外債務がない」との誓約書を差し入れてもらったが、購入から数年後に第三者から請求が来て簿外債務の存在が明らかになったとき
客観的起算点:株式売買時
主観的起算点:誓約書に違反する事実(簿外債務)の存在を知ったとき
Q 当社は建設会社です。改正民法の施行日の1か月前に請負契約を結んでリフォーム工事を行いましたが、代金の支払期日は施行日の1週間後だった場合、請負代金債権の消滅時効については現在の民法(3年)と改正民法(5年)のどちらが適用されるのでしょうか。
A 改正民法の附則により、施行日前後の法律行為については、「経過措置」(旧法と新法のどちらが適用されるかを明確にする規定)が置かれています。
消滅時効との関係では、基本的に、施行日前に債権発生の原因となる契約(今回は工事請負契約)が締結されていれば、この債権について「旧民法」が適用されることになります。
そのため、上記の場合は「支払期日から3年」で時効が完成しますが、もし施行日後に契約を締結していた場合には、時効期間は5年となります。
Q 労働基準法では、賃金請求権の時効期間は2年となっていますが、民法改正を受けて5年に延長されるのでしょうか。
A 賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会において、現在、賃金請求権等の時効期間の延長が議論されています。
まだ結論は出ていませんが、論点整理(案)を見る限り、一定の延長がなされる可能性が高いと考えられますので、今後の動向に注意が必要です。
Q 保険金請求権の時効期間も延長されますか。
A 保険金請求権は、保険法により時効期間が3年と定められています。
現時点では、民法改正を受けた保険法の規定の変更はありませんので、従来どおり3年で消滅時効にかかります。
Q 製造物責任法に基づく損害賠償請求権の時効期間も延長されますか。
A 製造物責任法(PL法)では、メーカーなどに対する損害賠償請求権の時効期間が「損害及び賠償義務者を知った時から3年」または「製造物を引き渡したときから10年」と定められています。
今回の民法改正により、製造物責任法の一部が改正され、「知った時から3年」が「5年」に延長されましたが、「製造物を引き渡したときから10年」の期間に変更はありません。
2 生命・身体の侵害による損害賠償請求権
(1)損害賠償請求権の種類
① 債務不履行に基づく損害賠償(契約違反など)
② 不法行為に基づく損害賠償(事故など)
①と②の違いは、相手との間に「契約関係」があるかどうかです。例えば、売主Aと買主Bとの間で「2019年7月1日までに、AがBに対して商品Xを1000個引き渡す」との合意(契約)が存在したもにもかかわらず、Aが期日までに納品をしなかった場合には、AはBに対して債務不履行(契約違反)を理由とする損害賠償責任を負います。
これに対し、Aが自動車を運転中にハンドル操作を誤り、歩行者Bをはねてしまったような場合には、当事者間には何らの契約関係がないため、AのBに対する債務不履行は存在しません。しかし、Aは、自らの過失によってBに損害を与えていることから、Bに対して不法行為(故意・過失によって相手に損害を与える行為)を理由とする損害賠償責任を負います。
ただし、特に業務上のトラブルでは、会社について、債務不履行責任と不法行為責任の双方が発生する可能性がありますので、念のため注意が必要です。
(例)
職場内で起きた従業員同士の事故で、会社が従業員に対して十分な安全配慮措置を行っていなかったようなケース
従業員C(被害者)→従業員D(加害者):不法行為に基づく損害賠償責任を追及
従業員C(被害者)→会社:従業員D(加害者)の使用者責任(不法行為)と、会社の安全配慮義務違反(債務不履行)に基づく損害賠償責任を追及
職場内でセクハラ・パワハラが行われたようなケース
従業員C(被害者)→従業員D(加害者):不法行為に基づく損害賠償責任を追及
従業員C(被害者)→会社:従業員D(加害者)の使用者責任(不法行為)と、会社の職場環境配慮義務違反(債務不履行)に基づく損害賠償責任を追及
(2)時効期間の延長(生命・身体の侵害を伴う場合)
改正前の民法では、債務不履行・不法行為によって発生した損害の内容にかかわらず、①債務不履行に基づく場合には「権利を行使することができるときから10年」、②不法行為に基づく場合には「損害および加害者を知ったときから3年」または「不法行為のときから20年」との時効期間を設けていました。
しかし、命の危険や怪我を伴うケースではより手厚い保護が必要になること、また、治療が長期間にわたるなどの事情により、被害者が迅速に権利行使をすることが難しいケースもあることから、今回、生命・身体の侵害を伴う損害賠償請求権について、以下のとおり時効期間を延長しています。
① 債務不履行:権利を行使することができる時(客観的起算点)から「10年」→「20年」に延長
② 不法行為:損害および加害者を知った時(主観的起算点)から「3年」→「5年」に延長
Q 当社は、施行日の2年前に起きた従業員同士の社内事故について、ケガをした従業員から会社の不法行為責任(使用者責任)を問われるリスクがあります。この場合、損害賠償請求権の消滅時効は、改正前後のどちらの民法の規定が適用されるのでしょうか。
A 上記のケースでは、被害者は、事故発生と同時に「損害および加害者を知った」ものと考えられますので、改正前の民法に基づく消滅時効期間は、事故発生日から3年間(施行日の1年後まで)です。
そして、施行日時点において消滅時効が完成していない場合には、経過措置により、生命・身体の侵害による損害賠償請求について改正民法の規定が適用されることになるため、上記の時効期間は「損害および加害者を知った時」(事故発生時)から5年に延長されます。
3 時効の中断・停止の見直し
もし、取引先が約束どおりに売掛金を支払ってくれないようなケースでは、将来の回収に向けた債権管理が必要になります。
この場合には、対象となる債権について、法的な権利が消滅しないようにすること(=消滅時効を完成させないこと)が重要になりますが、改正前の民法では、そのための制度として時効の「中断」「停止」が存在しました。
中断:法律で定める中断事由が発生した場合に、それまでに経過した時効期間をリセットし、ゼロに戻す制度。中断事由が終了した後は、改めて、新しい時効期間が進行する(時効期間の更新)。
停止:時効の中断を妨げる一定の事情がある場合に、その事情が消滅した後、一定期間が経過するまでの間は時効の完成を猶予する制度(時効の完成猶予)。
しかし、この「中断」「停止」という言葉からは、「時効期間のリセット(更新)」「完成猶予」という法的な効果が伝わらず、制度の内容がわかりにくいという批判がありました。
そのため、改正民法では、「中断」「停止」という表記を「更新」「完成猶予」に言い換え、併せて、更新事由・完成猶予事由に当たる行為を明確にしています。
(改正民法での時効の更新・完成猶予事由)
① 裁判上の請求等(裁判での請求、支払督促、訴訟上の和解、調停、破産手続への参加等)
② 強制執行等(差押、抵当権の実行による競売等)
③ 仮差押え等(仮差押え、仮処分)
④ 催告(請求書の送付等)
⑤ 協議を行う旨の合意
⑥ 承認(債務承認、債務の一部についての弁済等)など
Q 上記以外に、一定の期間、時効の完成が猶予されるケースはありますか。
A 例えば以下のような場合や、相手方が未成年者や成年被後見人であった場合、天災等が生じた場合には、一定の期間、時効の完成が猶予されます。
① 夫婦の一方が相手に対して権利(慰謝料請求権・貸金返還請求権等)を持つ場合には、離婚から6か月経過するまでの間、時効が完成しない。
② 貸金契約の借主が死亡した場合には、相続人が確定してから6か月経過するまでの間、時効が完成しない。
Q 当社の取引先は、業績不振を理由に売掛金100万円の支払いを先延ばしにしています。この売掛金については、今年の7月末で消滅時効が完成してしまうため、当社は、取引先と話し合い、まずは7月1日に一部返済金(10万円)の支払いを受け、残金90万円については、今年の8月1日以降に改めて支払方法を協議することにしました。この場合には、10万円の受領によって、売掛金の消滅時効が中断したことになるのでしょうか。
A 取引先は、売掛金の総額が100万円であることを前提に、その一部(10万円)を貴社に支払っています。この場合には、10万円の支払いが債務の「承認」(一部承認)に当たり、残りの売掛金債権(90万円)について時効中断の効果が発生します。具体的には、残債権について、10万円を受領した日の翌日から新たな時効期間が進行しますので、今年の7月末で貴社の権利が消滅することにはなりません。
Q 請負代金を支払わない取引先について、預金の仮差押え手続きを行いました。この場合には、いつまで消滅時効の完成がストップするのでしょうか。
A 仮差押えを行った場合には、その手続きが終了した後6か月を経過するまでの間、時効の完成が猶予されます。更に時効の進行を止めたい場合には、仮差押えの終了から6か月以内に、改めて裁判を起こすなどの対応を取らなければなりません。
Q 2016年5月に建設工事を行い、同年8月末に工事代金100万円の支払いを受ける予定でしたが、発注者が資金繰りの悪化を理由に代金を支払わないため、毎月、未払いの100万円について会社から請求書を郵送しています。この場合、工事代金100万円の債権は時効により消滅するのでしょうか。
A 改正前の民法では、建設工事代金は3年で消滅時効にかかるため、2016年8月末が支払い期日であれば、2019年8月末に消滅時効が完成します。そのため、それまでに時効の完成をストップさせる必要がありますが、「請求書の送付」だけでは時効の進行は止まらず、送付から6か月以内に別の手続を取る必要があります。
Q 相手方に対して毎月請求書を発行していれば、消滅時効は完成しないと聞いたのですが。
A 取引先に対して請求書を発行する行為は、民法上の「催告」(さいこく)に当たります。この場合には、催告の時から6か月を経過するまでの間、時効の完成が猶予されますが、その効果は1回限りのものです。更に時効の進行を止めたい場合には、催告から6か月以内に、改めて裁判を起こすなどの対応を取らなければなりません。
Q 時効の「完成猶予」事由として、新たに追加されたものはありますか。
A 「権利について協議を行う旨の合意」が追加されました。
改正民法では、代金の不払いなどが生じている場合に、債権者・債務者間で「権利について協議を行う旨の合意」をし、これを書面にした場合には、以下のいずれか早い時期までの間、時効の完成が猶予されると定められました。
① 合意があった時から1年を経過したとき
② 合意において1年未満の協議期間を定めた場合には、その期間が経過したとき
③ 一方から協議を打ち切る旨の書面による通知がなされ、その通知から6か月を経過したとき
Q 「権利について協議を行う旨の合意」は、どのような場面を想定しているのでしょうか。
A 未払代金の存在や金額など、債務の存在・内容について争いがない場合には、相手方に債務を「承認」(時効の更新事由)してもらうことが考えられます。これに対し、債務不履行の存在自体は争いがないものの、損害の範囲に争いが生じているようなときは、時効の完成をストップするため、「権利について協議を行う旨の合意」を行うことが考えられます。
Q 取引先が債務の存在や内容を争っている場合でも、書面で「権利について協議を行う旨の合意」を行えば、時効の完成が猶予されるのでしょうか。
A 「権利について協議を行う旨の合意」は、債務の存在や内容に争いがある場合でも、書面で作成されれば時効の完成猶予事由に該当します。
Q 「権利について協議を行う旨の合意」をしたものの、1年以内に話し合いがまとまらなかった場合には、期間の経過前に再度合意をすれば、猶予期間を延長できるでしょうか。
A 猶予期間の延長は可能ですが、トータルの期間は、当初の時効完成予定日から5年を超えることができません。
参考:「催告」(裁判外での請求の意思表示)の場合には、再度の催告による猶予期間の延長は不可
Q 「権利について協議を行う旨の合意」について、その他に留意が必要な点はありますか。
A 催告との関係に注意が必要です。
債務者に対する「催告」(裁判外での請求の意思表示)を行った場合には、6か月間、時効の完成が猶予されます。しかし、この猶予期間中、重ねて「権利について協議を行う旨の合意」をしたとしても、新たな時効完成猶予の効力は生じません。(逆に、「権利について協議を行う旨の合意」を行った後、猶予期間が終了する前に「催告」を行った場合も同様です。)
(例)
① 時効完成の1か月前に催告をしたが、その1週間後に相手から協議の申し入れがあったため、書面で「権利について協議を行う旨の合意」を取り交わし、協議期間を6か月と定めて話し合いを行ったとき。
② 未払いの取引先と「権利について協議を行う旨の合意」を取り交わしたが、1年の猶予期間内に話し合いがまとまる見込みがなく、また、相手方が再度の合意にも応じないため、当面の時間稼ぎとして「催告」を行ったとき。
Q 改正民法の施行日前に発生した債権について、「権利について協議を行う旨の合意」による時効の完成猶予は可能でしょうか。
A 施行日前に発生した債権でも、施行日後に「権利について協議を行う旨の合意」をし、これを書面にした場合には、改正民法による時効完成猶予の効力が認められます。
➡ 法定利率
➡ 定型約款