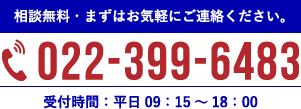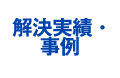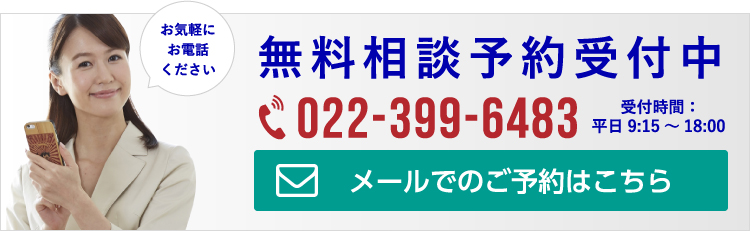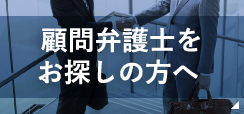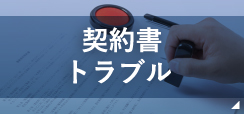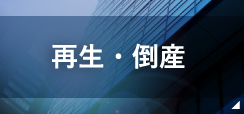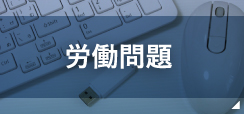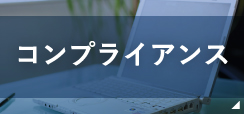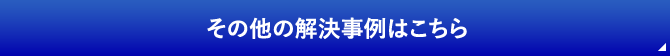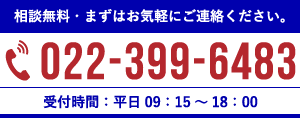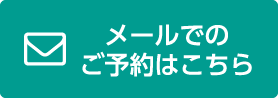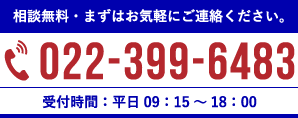会社の法律相談Q&A
Q 当社は、譲渡制限株式の発行会社です。株主Aから、A名義の当社株式をBに売却するとの連絡がありましたが、当社はBと関係があまり良くなく、どのように対応すべきか悩んでいます。
A 株主AからBへの株式譲渡を希望しない場合には、会社として、当該譲渡を承認しないことができます。
譲渡制限株式の発行会社では、株式の譲渡に当たり、概要以下のような手続きが予定されています。
① 株主は、会社に対し、株式数や譲受人の氏名等を明らかにして、株式譲渡の承認請求を行う
② 会社は、株主総会または取締役会の決議により、株式譲渡を承認するか否かを決定する
③ 会社は、株主に対し、株式譲渡の承認・不承認に関する通知を行う
(注)株主総会、取締役会のどちらの決議が必要になるかは、定款の記載に従います。
株主AからBへの株式譲渡を拒むときは、原則として、Aの請求から2週間以内に、Aに対して不承認の通知をしなければいけません。この期間を過ぎると、会社は譲渡を承認したものとみなされますので、注意してください。
また、株式譲渡を承認しない場合には、会社は、当該株式を自ら買い取るか、会社の指定する者に買い取らせる必要があります。この際には、Aに対し、所定の期間内にその旨を通知したり、法律で定める買取金額を供託するなどの手続が求められますので、お困りの場合にはお近くの専門家にご相談ください。
なお、株主Aが上記①の手続きを行わない場合には、会社は、引き続きAを株主として取り扱うことができます。
Q 当社は、譲渡制限株式の発行会社です。取締役Aが退任するため、Aの保有する当社株式を買い取ることにしました。どのような手続きを取ればよいでしょうか。
A 特定の株主から自己株式を買い取る場合には、以下の手続きが必要になります。
① 全株主に対し、株主Aからの自己株式の取得を目的とした「株主総会の招集」と「売主追加請求権」(注1)に関する通知を行う
② 他の株主B、Cから売主追加請求があった場合には、株主B、Cについても株主総会の議案の「売主」に追加する
③ 株主総会において、自己株式の取得に関する特別決議(注2)を行う
④ 特別決議の範囲内で、自己株式の取得に関する取締役(会)決議を行う
⑤ 株主A、B、Cに対し、買取り通知を行う
(注1)売主追加請求権:A以外の株主が、自分の保有する株式も買取りの対象に追加するよう会社に要請する権利
(注2)特別決議:議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要となる決議
会社が自己株式を買い取る場合には、売主に対して出資金の払戻しを行うのと同様の効果が生じます。会社法には「株主平等の原則」が定められているため、会社が株主Aに買取り(出資金の払戻し)の機会を与える場合には、他の株主との関係でも同等の取扱いをしなければなりません。このような理由から、上記①~⑤の手続きが定められています。
なお、自己株式の取得は、会社法で定める財源規制(買取金額の上限)の範囲で行う必要があります。また、株主への通知や決議内容等についても一定の要件が定められていますので、お困りの場合にはお近くの専門家にご相談ください。
Q 当社は、譲渡制限株式の発行会社です。取引先のA社から資本提携の申し出があったため、新株を発行してA社に引き受けてもらう予定ですが、どのような手続きが必要でしょうか。
A 会社が、特定の第三者に対して新株を発行することを「第三者割当増資」といいます。この「第三者割当増資」を行うためには、以下のような手続きを取る必要があります。
① 株主総会を招集する
② 株主総会において、募集株式の数、払込金額、払込期日等の「募集事項」を決定する
③ A社との間で、総数引受契約(発行する新株をA社が全て引受ける契約)を締結する
④ A社が株式の代金を払い込む
(注)総数引受契約の代わりに、(ⅰ) 会社から第三者に対する募集事項の通知、(ⅱ) 第三者による引受けの申込み、(ⅲ) これに対する会社の割当決定(第三者に引き受けてもらう株式数等の決定)、という手続きを取ることも可能です。今回は、手続きを簡略にするため、引受人が1名の場合によく行われる総数引受契約による対応を前提にしています。
会社が、特定の第三者に対して新株を発行した場合には、発行済みの株式総数が増加し、既存の株主の持ち株比率が下がることになります。
例えば、発行済みの株式数が100株の会社で、株主ABが50株ずつ株式を持ち合っていたケースを考えてみましょう。この場合、会社がCに100株の第三者割当増資をすると、50%だったABの持ち株比率は25%に低下し、他方で、Cは発行済み株式総数の半分を手に入れることになります。また、ABのうち1人の協力が得られれば、Cが会社の実権(株主総会での議決権の75%)を握ることも可能になり、株主間の力関係が変動する可能性もあります。
このように、第三者割当増資は既存の株主にも重大な影響を与えるため、上記②の株主総会では、特別決議(議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上が賛成する決議)による手続が必要とされています。
Q 当社は、創業者である父が代表を務めていますが、最近、高齢のため体調が思わしくありません。家族は父と母、兄と私の4名ですが、兄は県外に暮らしており、家業は次男の私が継ぐ予定です。どのような準備をしたら良いでしょうか。
A 事業承継に当たっては、特に、創業者が所有する株式の取扱いが問題になります。
創業者が200株の株式を所有しており、生前に相続対策を行うことなく亡くなった場面を考えてみましょう。この場合、創業者の所有する株式は、妻と息子が法定相続分(妻:1/2、子:各1/4)に従って相続しますが、これにより妻が100株、息子が各50株の株式を取得するわけではありません。相続人は、持分割合に応じて、200株の株式全体を「共同で所有」する権利を持ちます。そのため、議決権を行使する場合には、共有者間で代表者(権利行使者)を定めて会社に届け出るなどの対応が求められます。
このような状態を解消するには、相続人間で協議し、共有者の一人(後継者)が他の相続人の共有持分を買い取る必要が生じますが、残念ながら円満に解決しないこともあります。創業者がご健在なうちに、株式の生前贈与や遺言書の作成(後継者への株式の遺贈)など、必要な事業承継対策を取ることをお勧めします。一定の要件を満たす場合には、税制面での優遇など中小企業に向けた支援措置もありますので、お近くの専門家にご相談ください。
なお、本社の敷地や建物が創業者の個人名義になっているような場合にも、同様の注意が必要です。
Q 万が一の場合に備えて、私が所有する当社株式を後継者(子)に相続させる遺言を作成しようと思います。どのような方法がありますか?
A 遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があり、一般的には①又は②の方法が取られます。
① 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言の作成者が、その内容と日付、氏名を自書して捺印したものをいいます。原則として手書きによる必要がありますが、財産目録だけは、パソコンで作成したものを添付することが可能です。この場合には、財産目録のページ毎に、手書きで署名捺印をしなければなりません。
作成した遺言書は、自宅で保管したり、手数料を払って法務局に預けることができます。但し、自宅保管の場合には、開封前に家庭裁判所で「検認」という手続を取る必要があります。
② 公正証書遺言
公正証書遺言とは、法務大臣が任命する「公証人」の関与を受けて作成する遺言です。遺言者は、遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを書面にします。最後に、遺言者と証人2名がその内容を確認し、間違いがなければ公正証書に署名捺印をして遺言手続きが終了します。作成した遺言書は、公証役場で原本を保管し、遺言者には写し(正本)が渡されます。
上記①②の方法には、それぞれメリットとデメリット(手軽さ、費用負担、有効性の争われやすさ、検認手続きの要否等)があります。財産の種類や遺言の内容、相続人間の関係性等を考慮し、事情に応じた選択を行うことが重要になりますので、必要に応じてお近くの専門家にご相談ください。
Q 私は会社を経営しており、個人で所有する土地建物を会社に賃貸しています。将来に備えて、後継者(長男)に主な財産を相続させる遺言を作成しようと考えていますが、相談した友人から「遺留分に気を付けた方がよい」と言われました。遺留分とは何でしょうか?
A 遺留分(いりゅうぶん)とは、亡くなった方の配偶者や子ども、親など一定の相続人に保障される最低限の相続財産のことをいいます。
遺留分は民法で定められた権利であり、遺言書の内容にかかわらず、遺留分の権利を持つ相続人は一定の相続財産を取得することができます。ただし、兄弟姉妹が相続人の場合には遺留分はありません。
例えば、Aが「全財産を長男に相続させる」という遺言書を作成して亡くなったケースを考えてみましょう。亡くなった当時、Aには配偶者Bと長男C、長女D、次男Eがいたとします。Aの遺言によれば、相続財産はすべて長男Cが受け継ぐことになりそうですが、この場合でも、他の相続人は長男Cに対し、民法に従って遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。
このような相続トラブルを避けるためには、事前にB、D、Eの遺留分を確認し、遺言書の内容をBらの遺留分を侵害しない形に変更するなどの対応が考えられます。
遺留分の割合は民法に定められていますが、事例のように配偶者と子ども3名が相続人の場合には、配偶者の遺留分は相続財産の1/4、子どもは各1/12になります。 遺留分について詳しい内容をお知りになりたい場合には、お近くの専門家にご相談ください。
Q 当社は、個人向けの住宅リフォーム等を行う株式会社です。お客様の自宅を訪問してリフォーム契約を締結した2週間後に、クーリング・オフの申し入れがありました。法定のクーリング・オフ期間(8日間)は経過していると思いますが、応じなければならないのでしょうか?
A 一定の場合には、法定期間が経過した後でも、クーリング・オフが認められるケースがあります。
クーリング・オフとは、契約書面等(法定書面)を交付した日から一定の期間に限り、無条件で契約の解除を認める制度です。訪問販売の場合には、クーリング・オフ期間は8日と定められているため、契約から2週間が経過していれば「もう大丈夫」と思われるかもしれません。
しかし、特定商取引法では、この「法定書面」に記載すべき事項を細かく指定しており、一部の記載が抜けていたときは、クーリング・オフ期間の進行に必要な「法定書面」の交付がなかったものとして取り扱われます。この場合には、必要事項を充足した書面が交付されるまでの間、クーリング・オフ期間(8日)は開始せず、顧客はいつでも契約の解除をすることができます。
【記載が必要な事項】
商品の価格、支払時期・方法、引渡時期、クーリング・オフの告知(赤枠・赤字で表示)、事業者の名称・住所・電話番号・代表者の氏名、担当者の氏名、契約日、商品の型式など
裁判例では、法定書面の記載事項のうち「法人代表者の氏名」や「販売担当者の名」が抜けていたため、契約日から約2か月が経過した後のクーリング・オフを認めた事例もありますので、ぜひご注意ください。
Q 当社は、時計の修理を専門に行う株式会社です。修理中に不測の事態が発生した場合に備えて、契約書に「当社は、お客様に生じた損害について一切の責任を負いません」という条項を入れたところ、お客様からこのような規定は無効だと言われました。
A 現在の条項は消費者契約法に違反して無効となるため、内容を変更する必要があります。
契約書の中に、事業者の債務不履行が原因で消費者に損害が生じた場合に、事業者の賠償責任をすべて免除する条項を入れたとしても、当該条項は消費者契約法により無効となります(8条1項1号)。
そのため、債務不履行の有無を問わず、事業者が「一切の責任を負わない」とする条項は効力を持ちません。また、同様の観点から、事業者に「故意」または「重過失」がある場合に、事業者の責任の一部を免責する条項も無効になります(同2号)。
なお、実務では、「当社が負う損害賠償責任の範囲は、金〇〇円を上限とします」等、事業者の責任を一定の範囲内に制限する条項をよく見かけます。従来は、このような場合にも、消費者契約法で無効となる範囲を除いて条項どおりの効力(一部の免責)が認められるケースがありましたが、法改正(2023年6月施行)により、当該規定は無効として扱われます(同法8条3項)。
このような事態を避けるためには、必ず、「当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社が負う損害賠償責任の範囲は、金〇〇円を上限とします」など、当該条項が事業者に「軽過失がある場合」のみに適用されることを明らかにする必要がありますので、ご注意ください。
Q 当社は、インターネットで健康食品やサプリメントを販売しています。法改正により、定期購入に関する取引への規制が厳しくなったと聞きました。どのような点が変わるのでしょうか?
A 通販サイトでの販売にあたって、取引内容を消費者に分かりやすく表示することが必要になりました。
定期購入に関するトラブルの増加を受けて、特定商取引法が改正され、2022年6月1日から新たな取引規制が設けられました。この法改正により、事業者は、定期購入商品について、最終確認画面で以下のような事項を表示する義務を負います。
【表示が求められる事項】
① 各回に引き渡す商品の数量
② 引渡し回数
③ 各回の代金
④ 代金の総額
⑤ 各回の代金の支払時期及び方法
⑥ 各回の商品の引渡時期など
上記以外にも、事業者に対しては、返品や解約時の連絡方法・連絡先、返品や解約の条件等を消費者が見つけやすい位置に表示することや、期間限定販売を行う場合は、その申込み期限を表示するなどの対応が求められます。
これらの義務に違反した結果、消費者が取引内容を誤認して申し込みを行った場合には、定期購入に関する契約の取消しが認められる可能性があります。
また、特定商取引法では、事業者が行う取引内容の表示について、法令やガイドラインで詳細なルールを設けていますので、対応に悩む場合にはお近くの専門家にご相談ください。
Q ライバル会社に人材が流出するのを防ぐため、従業員に対し、退職後は競合他社に就職しないという誓約書への署名捺印を求めようと思います。何か注意が必要な点はありますか?
A 誓約書の内容によっては、後日トラブルになった場合に、裁判所から合意の効力を否定されるリスクがあります。
従業員は、会社の秘密情報を使用して事業活動を行うため、退職後に競合他社に就職した場合には、自社の秘密情報が流出したり、自社の競争力が大きく低下するなどの可能性があります。そのため、上記のような誓約書を取得し、従業員に競業避止義務を負わせる取り組みが広く行われています。
しかし、従業員には「職業選択の自由」という憲法上の権利があります。そのため、従業員に競業避止義務を負わせたい会社と、自分の希望する会社に就職したい従業員の権利が衝突し、様々な場面で「どちらが優先すべきか」という問題が生じます。
この問題については、すでに多くの裁判で争われており、従業員から誓約書を取得した場合でも、競業避止義務の内容によってはその効力が否定されることが明らかになりました。具体的には、以下の6つの判断要素に照らして、競業避止義務の内容が「必要最小限度のもの」といえるかどうかが問題になります。
【判断要素】
① 守るべき企業の利益があること
② 従業員の地位(競業避止義務が必要な立場か)
③ 地域的な限定の有無
④ 競業避止義務の存続期間
⑤ 禁止される競業行為の範囲
⑥ 代償措置の有無
このうち①については、ライバル会社に人材が流出することにより、営業秘密や独自のノウハウなどが流出するリスクがあれば、「守るべき企業の利益がある」といえるでしょう。
また、②については、対象となる従業員が営業秘密に深く関与する立場あれば、競業避止義務を課す必要性が高くなります。
③④については、例えば、在職時に担当していた営業地域やその隣接地域に限って競業を禁止する場合や、競業避止義務の期間を退職後1年間に限定する場合などが考えられます。
⑤については、例えば競合他社への転職ではなく、在職中に担当していた顧客との取引に限って禁止するのであれば、競業避止義務は認められやすい傾向にあるでしょう。
⑥の場合には、競業避止義務を負うことを前提として退職労金や高額の給料が支給されている場合には、代償措置の存在が認められやすくなります。
このように、競業避止義務の有効性は、個別の事情に応じて結論が異なりますので、ご注意ください。最後に、ご参考として、競業避止義務が有効とされた事例、無効とされた事例の一部をご紹介します。
① 有効とされた事例
・ 退職後6か月、顧客への営業活動を禁止(東京地裁平成11年10月29日)
・ 退職後1年間、同業他社への転職等を禁止(東京地裁平成19年4月24日)
・ 退職後2年間、在職時に担当したことのある営業地域(都道府県)やその隣接地域での顧客への営業活動を禁止(東京地裁平成14年8月30日)
・
② 無効とされた事例
・退職後6か月間は場所的制限なしに、2年間は在職中の勤務地または「何らかの形で関係した顧客その他会社の取引先が所在する都道府県」での競業・役務提供を禁止(東京地裁平成24年3月15日)
・退職後3年間、同業他社への就職等を禁止(大阪地裁平成28年7月14日)
・退職後に同業他社に就職等した場合に、無期限に顧客への営業活動を禁止(福岡高裁令和2年11月11日)
なお、上記①のケースでは、いずれも、会社に営業秘密やノウハウ等の「守るべき利益」があり、これらの利益を守るために、従業員に一定の競業避止義務を負わせる必要性があることが前提とされています。そのうえで、対象となる地域や期間、禁止行為の範囲等を考慮し、退職後の競業避止義務が「必要最小限度」にとどまるかどうかを判断していますので、お悩みの場合にはお近くの専門家にご相談ください。
Q 発注書・受注書だけでは法的に不十分でしょうか?
A 記載内容によっては、法的に不十分になる可能性があります。
売買取引の場合には、最低限の条件として、売買の目的物や金額、支払条件、引渡日などを取り決めておく必要があります。発注書にも、上記の条件は記載されていることが多いですが、これだけでは思わぬ不利益が生じるリスクがあります。
例えば、民法上は、「物権(注:所有権)の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」とされています(176条)。つまり、原則として、売買の合意が成立した時点で(代金の支払いを待たずに)所有権が移転しますので、もし買主に不払いが生じた場合でも、売主は契約を解除しなければ目的物を取り戻すことができません。
このような不利益を避けるためには、当事者間で「所有権は、代金が完済されたときに売主から買主に移転する」と定める必要があります。
また、不払いが生じた場合の遅延損害金も、原則は法定利率(年3%をベースとする変動金利)に限られますので、実務上よく見かける「14.6%」への変更を行うためには別途の合意が必要です。このように当事者間で詳細な条件を取り決める場合には、発注書とは別途「取引基本契約書」を作成することをお勧めします。
Q 「売買基本契約書」と「売買契約書」は何が違うのでしょうか?
A 「売買基本契約書」と「売買契約書」には、以下のような違いがあります。
「売買基本契約書」は、通常、対象商品について、相手との間で行われる売買取引全般に適用されます。例えば、A社との間で継続的な取引を行っている場合には、売買基本契約の有効期間内に行われたすべての売買について、売買基本契約書に記載した取引条件が適用されます。
これに対し、「売買契約書」は、通常、1回限りの売買取引を対象とします。新たに売買取引を行う場合には、同じ相手であっても、別途契約条件を定める必要があります。
実務上は、得意先など、何度も取引を予定している相手方との間で「売買基本契約書」や「取引基本契約書」を取り交わし、すべての取引の条件が同一になるようにしておくことが多いでしょう。この場合でも、個々の取引を行うときは、売買の目的物や数量・金額等を特定した個別契約書の作成が必要になりますが、「売買基本契約書」に明記しておけば、発注書・受注書のやり取りで済ませることも可能です。
重要な取引条件は売買基本契約書でしっかりと確認し、個々の売買取引は発注書・受注書でスピーディーに行うなど、実務に即した対応が望ましいでしょう。
Q 「売買基本契約書」には、どんな条項が必要でしょうか?
A 実際の取引によって異なりますが、基本的には、①個別契約の成立、②商品の検査、③契約不適合責任、④所有権の移転、⑤代金支払、⑥損害賠償、⑦守秘義務、⑧契約期間、⑨解除、⑩権利義務の譲渡禁止、⑪合意管轄などを定めることが多いでしょう。
Q 「売買基本契約書」では、個別契約の成立・商品の検査についてどのような記載が必要でしょうか?
A 基本的には、以下のような内容を記載することが多いでしょう。
【個別契約の成立】
「個別契約の成立」では、例えば、個々の取引について、契約書ではなく発注書・受注書のやり取りで個別契約が成立することを記載します。
【商品の検査】
「商品の検査」では、引き渡した商品の種類・品質・数量が発注内容と一致するかについて、買主 が行う検査方法や期間、検査に合格・不合格だった場合の取扱いなどを定めます。
例えば、納品からしばらく経過した後に、買主から「数量に不足があった」「商品が壊れていた」などの指摘を受けた場合には、数量不足等が納品当時に生じていたものか(売主の責任)、それとも納品後に発生したものか(買主の責任)の判断が難しくなります。
そのため、契約書上、「買主は、納品後すみやかに商品の種類・品質・数量について検査を行う」「(数量等について)契約内容との不一致があった場合には、納品から〇営業日以内に売主に通知する」「この期間内に売主への通知がなかったときは、契約どおりの納品があったものとみなす」といった条項を記載し、買主に早期の確認と売主への通知を義務付ける対応が行われています。
特に、自社が売主となる場合には、納品後のトラブルを避けるために、このような規定を盛り込むとよいでしょう。
Q 「売買基本契約書」では、契約不適合責任についてどのような記載が必要でしょうか?
A 基本的には、以下のような内容を記載することが多いでしょう。
① 責任の内容
契約不適合責任とは、契約書の条項に従って納品された商品に「型番違い」「品質不良」「数量不足」などの不具合があった場合に、売主が負う責任のことをいいます。
購入した商品に上記の不備があったときは、買主は売主に対し、①代替物の引渡し、②目的物の修理、③不足分の引渡しを求めることができます。これらの対応をまとめて「履行の追完」と呼びます。
また、買主が履行の追完を請求したにもかかわらず、売主が一定期間内に応じない場合等には、買主は売主に対し、売買代金の減額や契約の解除を求めることができます。上記の不具合が原因で買主に損害が生じたときは、実際に発生した損害の賠償を請求することも可能です。
② 通知
売主の責任を追及するためには、原則として、商品の「不具合を知ったときから1年以内」(事業者間の取引の場合には6か月以内)に通知する必要があります。
③ ポイント
契約不適合責任は民法に基づく規定ですが、売主と買主が合意すれば、その内容を変えることができます。これを「任意規定」といいます。
具体的には、通知のための期間を短縮したり、消費者契約法などの法令に違反しない限り、売主の責任の全部または一部を免除することも可能です。契約書を作成するときには、契約不適合責任の内容についてもよく確認することをお勧めします。
Q 「売買基本契約書」では、所有権の移転・代金支払についてどのような記載が必要でしょうか?
A 基本的には、以下のような内容を記載することが多いでしょう。
【所有権の移転】
法律上は、「物権(注:所有権)の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」とされています(民法176条)。売買はこの「所有権の移転」に該当するため、当事者の合意が成立した時点で、売主から買主に所有権が移転するのが原則です。
しかし、実務上は、商品の引渡しによって所有権を移転するケースが多く見られます。このような場合には、「代金の支払い」を引渡しの条件としたうえで、「商品の所有権は、引渡しと同時に買主に移転する」などの条項を盛り込む必要があります。
ただし、掛売の場合には、一般的に、代金の支払い前に買主に納品を行います。そのため、上記のように「引渡し」を所有権の移転時期とした場合には、後日代金の不払いがあっても、所有権を理由に商品の引き揚げを求めることができません。
このようなケースでは、①所有権の移転時期を「代金の完済時」とする、②買主との間で、代金完済までの間は売主に所有権を留保する特約を結んでおく、などの対応が必要になります。
【代金支払】
代金の支払いについては、前払い・同時払い・後払い(売掛)といった支払方法や、一括払い・分割払いの区別、支払時期・回数などを記載します。これらの内容は、通常の発注書・受注書にも含まれるものですので、同様の記載を行えばよいでしょう。
Q 「売買基本契約書」では、損害賠償についてどのような記載が必要でしょうか?
A 基本的には、以下のような内容を記載することが多いでしょう。
損害賠償とは、故意や過失によって相手に損害を与えた場合に、その損害を補償することをいいます。損害賠償に関する条項については、以下のような定め方があります。
① 軽過失の免責
民法では、「過失」(不注意)により発生した損害についても賠償が必要になりますが、契約書に次のような規定を設けた場合には、軽度の不注意を免責することができます。
(例)甲(自社)は、故意又は重大な過失により乙に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負う。
② 賠償額の限定
自社が支払う賠償額に上限を設けたい場合には、以下のような条項を置くことも可能です。ただし、相手が個人(消費者)の場合には、消費者契約法による制約があり、「故意」や「重過失」の場合には免責されないことを明確にする必要がありますので、ご注意ください。
(例)甲(自社)が負う損害賠償の範囲は、金○円を上限とする。
③ 損害の範囲
紛争解決のために発生した弁護士費用は、「損害」として認められにくい傾向があります。そのため、弁護士費用を含めた金額を請求したい場合には、事前に「損害(弁護士費用を含む)」と規定しておく必要があります。
また、取引上、発生が予想される損害が決まっているような場合には、その項目を明記しておくとよいでしょう。
Q 「売買基本契約書」では、守秘義務についてどのような記載が必要でしょうか?
A 基本的には、以下のような内容を記載することが多いでしょう。
事業者間では、取引に関連して技術・ノウハウ等の秘密情報が開示されることがありますが、これを保護するための規定が「守秘義務」条項です。本条項で主要なポイントになるのは、①秘密情報の範囲、②義務の内容、③除外事由、④対象期間です。
【秘密情報の範囲】
守秘義務条項では、まず「秘密情報」の範囲を明確にします。例えば、「本契約に関して知り得た相手方の技術上または営業上その他一切の情報」と定めるケースもありますが、この場合には開示された情報すべてに守秘義務が発生するため、受領者の負担が重くなります。自社が情報を受け取る側であれば、秘密情報を「相手方が秘密である旨を明示して開示した情報」に限定するなどの対応が望ましいでしょう。
【義務の内容】
第三者への開示禁止、目的外使用の禁止、秘密情報の返還等を定めることが一般的です。
【除外事由】
形式上は「秘密情報」に当たる場合でも、一般に知られている情報等であれば保護の必要性はありません。そのため、①公知情報、②開示時に受領者が保有していた情報、③第三者から適法に取得した情報、④独自に開発・取得した情報などは「秘密情報」から除外するのが一般的です。
【対象期間】
契約上の義務は、その契約の終了に伴って消滅するのが原則です。しかし、秘密情報は会社の重要な財産ですので、自社が開示する側であれば、「(守秘義務条項は)契約終了後も○年間有効に存続する」などの規定を盛り込むことが望ましいでしょう。
Q 「売買基本契約書」では、契約期間・解除についてどのような記載が必要でしょうか?
A 基本的には、以下のような内容を記載することが多いでしょう。
【契約期間】
「契約期間」については、一定の期間以外に、必要に応じて「自動更新」に関する条項を追加します。自動更新条項を入れた場合には、期間満了後も、契約を結びなおすことなく取引を継続することができます。
【解除】
「解除」については、まず、解除の原因となる「解除事由」を定めます。具体的には、契約違反や信用不安等を記載し、解除事由が発生した場合には、必要に応じて契約を終了できる手段を整えておきます。
また、解除の方法には、相手に是正の機会を与える「催告解除」と、是正の機会なく直ちに解除を行う「無催告解除」の二種類があります。一般的には、代金延滞など一定の猶予を設けた対応が可能な場合には「催告解除」、相手の信用不安など重大なリスクが発生した場合には「無催告解除」とするケースが多いでしょう。
(例)催告解除
甲または乙は、相手方が本契約の定めに違反し、履行の催告を行った後も相当期間内に是正しない場合には、本契約の全部または一部を解除することができる。
(例)無催告解除
甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合には、前項の催告をすることなく、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
① 支払停止または支払不能になったとき
② 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算手続開始の申立があったとき
(以下略)
Q 「売買基本契約書」では、権利義務の譲渡禁止・合意管轄についてどのような記載が必要でしょうか?
A 基本的には、以下のような内容を記載することが多いでしょう。
【権利義務の譲渡禁止】
権利義務の譲渡禁止とは、相手の承諾なく、契約上の地位(売主・買主としての地位)や権利義務(代金請求権・支払義務等)を第三者に譲渡できないことをいいます。
取引を行う場合には、通常、相手との関係性(能力、実績、信用力等)も考慮して契約の有無や条件を決定します。相手の実績や信用力を見込んで契約を締結した後、全く知らない第三者に契約上の地位や権利義務が譲渡された場合には、期待どおりの商品やサービスが提供されない、商品やサービスを提供しても代金の支払いが受けられない等のリスクが生じます。
このような事態を避けるためには、あらかじめ、契約書の中で権利義務の譲渡禁止に関する条項を定めておくことが一般的です。
【合意管轄】
合意管轄とは、将来、相手との間で紛争が発生した場合に備えて、提訴する裁判所を事前に合意しておくことをいいます。
法律では、会社を被告とする場合、原則として、相手方の本店所在地を管轄する裁判所に訴えを起こす必要があります。ただし、未払金や損害賠償等を請求するときは、原告は、別途、債権者の住所地や不法行為地の裁判所に対しても訴訟を提起することができます。
遠方や予期しない場所での裁判手続を避けるため、実務上は、契約書に裁判管轄に関する専属的な規定を設け、当事者で合意した裁判所のみを管轄に指定する対応が取られています。