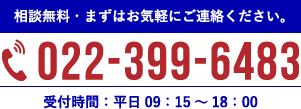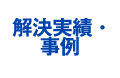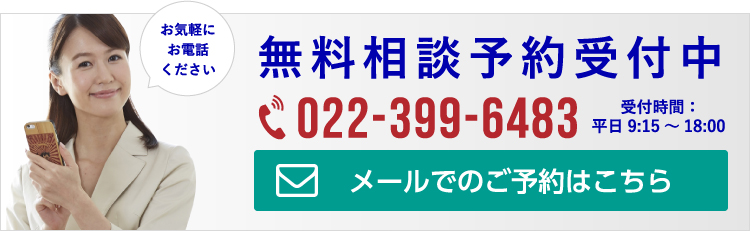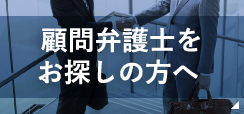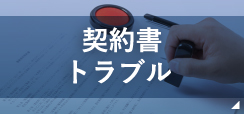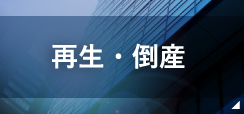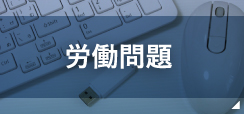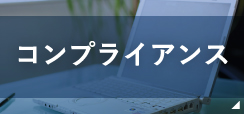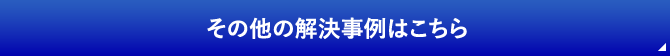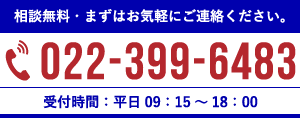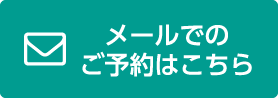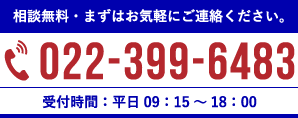社外相談窓口(ハラスメント・内部通報)をお探しの方へ
パワハラ防止法の施行
2020年6月1日施行の労働施策総合推進法(改正)により、以下のとおり、すべての企業に対して「ハラスメント相談窓口」の設置が義務化されました。
【労働施策総合推進法の改正】
(1)2019年5月
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」改正
(いわゆる「パワハラ防止法」)
☞ 事業主に対し、職場におけるパワーハラスメントを防止するために「雇用管理上講ずべき措置」
の実施を義務付け
(2)2020年6月1日(施行日)
大企業について、「雇用管理上講ずべき措置」を義務化
ただし、中小企業については、2022年3月31日まで適用を猶予(努力義務)
(3)2022年4年4月1日以降
中小企業について、「雇用管理上講ずべき措置」を義務化
事業主が講ずべき措置
上記の法改正では、事業主に対して、パワハラ防止のために以下の対策(雇用管理上必要な措置)を講じるよう求めています。
・ 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
・ 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・ 職場におけるパワーハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
・ 併せて講ずべき措置(プライバシーの保護・相談者への不利益的な取扱いの禁止)
これらの措置の内容は、合わせて10項目に及んでおり、そのすべてが「事業主の義務」とされました。
それぞれの詳細については、厚労省が公表している「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」をご参照ください。(厚労省の指針は、こちらのページからご確認いただけます。)
相談体制の整備
このように、事業主には、中小企業であっても「相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」が義務付けられています。
具体的には、厚労省の指針において、事業主は、以下の対応を取らなければならないと定められています。
【指針(抜粋)】
事業主は、労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するために必要な体制の整備として、次の措置を講じなければならない。
イ 相談への対応のための窓口(以下「相談窓口」という。)をあらかじめ定め、労働者に周知すること。
(相談窓口をあらかじめ定めていると認められる例)
① 相談に対応する担当者をあらかじめ定めること。
② 相談に対応するための制度を設けること。
③ 外部の機関に相談への対応を委託すること。
ロ イの相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、相談窓口においては、被害を受けた労働者が萎縮するなどして相談を躊躇する例もあること等も踏まえ、相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなどその認識にも配慮しながら、職場におけるパワーハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、職場におけるパワーハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応し、適切な対応を行うようにすること。
例えば、放置すれば就業環境を害するおそれがある場合や、労働者同士のコミュニケーションの希薄化などの職場環境の問題が原因や背景となってパワーハラスメントが生じるおそれがある場合等が考えられる。
(相談窓口の担当者が適切に対応することができるようにしていると認められる例)
① 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状況に応じて、相談窓口の担当者と人事部門とが連携を図ることができる仕組みとすること。
② 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留意点などを記載したマニュアルに基づき対応すること。
③ 相談窓口の担当者に対し、相談を受けた場合の対応についての研修を行うこと。
社外相談窓口の増加
ハラスメント相談・内部通報では、相談者が、氏名・相談を行った事実・内容等が内部に広まってしまうのではないかという不安や、会社から報復的な措置がされるのではないかという懸念を抱き、なかなか相談・通報に踏み切れない場面が多くあります。
また、事業主側でも、ハラスメント相談・内部通報の窓口対応に関するノウハウが乏しく、厚労省の指針で求められるような「相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにする」体制の整備に悩むケースが散見されます。
このような中、厚労省の指針で「相談窓口をあらかじめ定めていると認められる例」として、「外部の機関に相談への対応を委託すること」(上記イ③)が挙げられたことから、法律事務所や専門会社にハラスメント相談の社外窓口を依頼するケースが増えています。
弁護士を相談窓口にするメリット
ハラスメント相談・内部通報では、相談・通報があった事実や氏名の取扱いについて慎重な対応が求められ、内部で「相談者・通報者の特定」や「報復的な行為」が行われないよう細心の注意を払う必要があります。
また、ハラスメント・内部通報の調査に当たっては、調査対象者の選定や調査方法、調査の結果判明した事実に基づく判断(事実認定)について、相談・通報内容や職場の状況等を踏まえた検討が必要になり、専門的な対応が求められます。
よくご相談いただくケースでは、①内部で調査を行う前に、誰を調査対象にすればよいのか、具体的にどのような事項を聞けば良いのかなどを相談し、調査に漏れがないようにしたい、②ヒアリング調査によって判明した内容を弁護士に共有し、この内容から相談者・通報者の主張する「ハラスメント」「内部通報の事実」があったかどうかを相談したい、という場面が多くあります。
特に、「ハラスメント」「内部通報の事実」の判断については、裁判での事実認定の枠組みを踏まえて、仮に紛争(裁判等)になった場合にどのような結論となる可能性が高いかなど、将来的な対応も見通した対応が必要になります。
当事務所では、複数の事業会社・行政機関・公益財団法人等から外部窓口を受託しており、豊富な経験とノウハウを有しておりますので、外部窓口の設置をご検討の場合には、お気軽にご相談ください。